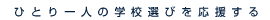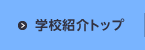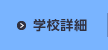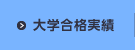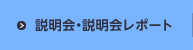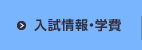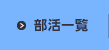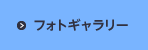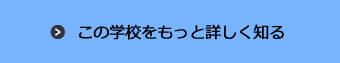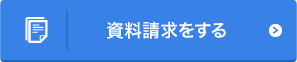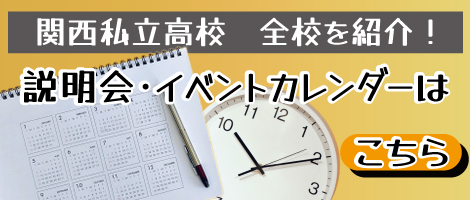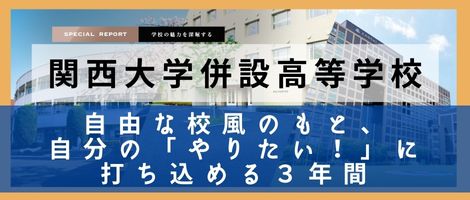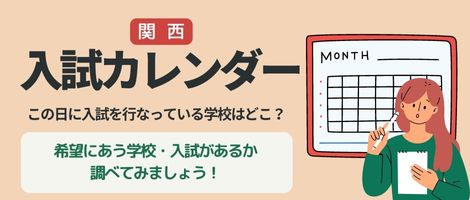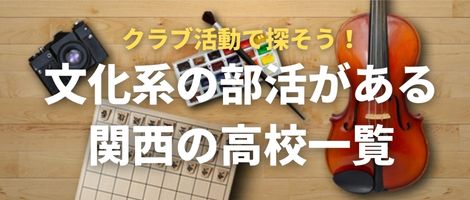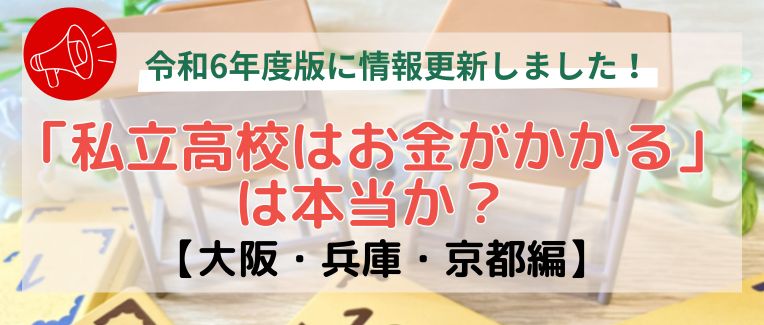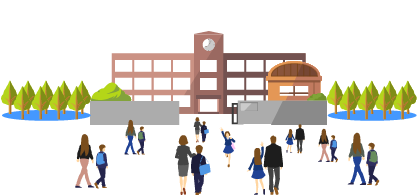スクール特集(四條畷学園高等学校の特色のある教育 #7)

青春”を原動力に、生きる力を育むナワガクの現在地
熱中できることを探して仮説を立て、挑戦する。その連続が生徒を変え、未来をつくる。勉強も探究も学校行事も、すべてが「青春」。偏差値だけでは測れない力強く生きる力を育てるナワガクの学びをレポートする。
大阪府にある四條畷学園高等学校が、近年、注目を集めている。2022年のコース再編をきっかけに、“偏差値だけでは測れない学び”を掲げた学校改革を進め、「青春しようぜ!」を合言葉に、挑戦と対話にあふれる学校文化を育んできた。SNSを通じた情報発信や企業との協働、大学生メンターとの対話など多彩な取り組みが今の時代にフィットし、高校受験生や保護者に響いているのである。数々のアイデアでナワガクを人気校に導いた広報部長の小山宣宏先生に話を聞いた。
「青春って何?」という問いかけが、価値観の発見に
「偏差値や進学実績は結果であって、教育の本質ではないと思っています。“自分がどうありたいか”を高校時代に問い続けること。そこに本校の教育の軸があります。その中で生徒一人ひとりがやりたいことを口にできるかどうか。それが進路の質を決める。だからこそ本校は、“やってみたい”を起点に教育プログラムを設計しています」と小山先生は話す。
同校には現在、三つのコースがある。総合キャリアコースは「好き」を深め、指定校推薦を中心とした進学をめざす。発展キャリアコースは、プロジェクト型の探究を通じて、自分の問いを言語化し、総合型選抜に挑戦する。特別シンガクコースは学力を軸に、一般入試に対応する進路設計が特徴だ。
中でも発展キャリアは“青春倍増計画”の名のもとに始動し、わずか3年で2クラスから5クラスへと増加した。
「問いの立て方から始めます。まず“青春ってなに?”って。生徒同士で話し合い、“これが私たちの青春”と定義づけてから、プロジェクトが動き出します。お化け屋敷をやりたい、修学旅行をプロデュースしたい…そんな発想が真剣な探究につながります」
もちろん、プロジェクトは遊びではない。チームで計画を立て、スケジュール管理や対外交渉を担い、実行後は振り返りとプレゼンを行う。その過程で生徒は、自然と「自分の問い」の中から「自分だけの価値観」を見つけ、それを進路へと結びつけられるようになるという。

▶︎広報部長 小山宣宏先生

企業や大学生と協業する開かれた高校
また小山先生は次のようにも話す。「多くの高校生は、問いを持つ機会がないまま、大学進学先を選んでいるように思います。大学を中退する一番の理由は“学びのミスマッチ”です。高校生のうちに、自分の“好き・得意・大事にしたいこと”を言語化できていれば、学びのミスマッチは回避できるはず」
そのための仕組みとして、同校では、大学生がメンターとして日常的に生徒と対話を重ねてをサポートする。また生成AIを活用し、自分の興味関心や価値観をもとに「将来の仮説」を立ててみる取り組みもなども実施し、仮説を立てて将来の自分にリアリティを持たせる。
「大切なのは、“仮説を持って動くこと”。合っているかどうかは問題ではない。やってみた結果、違ったならまた考え直せばいいんです。ナワガクの生徒はそういう“行動と思考の往復”を日常的に行っています」
また専門学校や企業との連携も、同校の強みの一つだ。テーマパークのキャスト講座、ラテアート体験、旅行会社や飲食チェーンとのコラボ企画など、生徒の興味関心を出発点とした実践的な取り組みが多数実現している。
これらのプロジェクトにおいて、ナワガク生の熱心な姿勢や自由な発想は、企業側にも若者のリアルなアイデアとして大いに貢献しており、互いに学び合う関係が成立している。社会とつながる経験は、単なるスキル獲得にとどまらず、自分の価値観を見つめ、自信を獲得する機会として、生徒一人ひとりの成長を後押ししている。

進路指導もナワガクイズムで
現在のナワガクの教育観は、進路指導のあり方にも反映されている。指定校推薦の評価基準に「挑戦してきた内容」や「自分の言葉で語れる力」を加点項目として明文化。偏差値や評定平均のみに依存しない“新しいルール”を提示している。
「行けるところに進むのではなく、行きたいから進む。進路はそうあるべきです。自分の“軸”を持って大学を選ぶ。だから本校では、総合型選抜の比率が年々増えています」(小山先生)
このような進路指導を実現するために、ナワガクの教育改革は今、教師の在り方についても変化が起きている。
「生徒の問いに寄り添うためには、教師自身も常に問いを抱いている必要があります。
『まずやってみよう』と声をかけられること。
『無理かもしれない』と決めつける前に、一緒に挑戦できること。
そんな姿勢こそ、教師にとって欠かせないものです。」
たとえば、教師が生徒を指導していた“身だしなみ指導”において「生徒が先生に“どう伝えたら受け入れられるか”を教える」逆転的な授業が実施された。「先生をしてくれた生徒が、ダメな例、良い例を交えながら、演劇のように見せてくれました。教員の方が学ばされましたよ」と小山先生。この授業では、女優志望の生徒が本領を発揮してくれたのだとか。また授業後の質疑応答では、たくさんのやり取りがあったそうだ。生徒と大人が共に学び合う学校。小山先生が考える理想が形になりつつある。
ナワガクの魅力を発信する生徒
同校には、生徒が学校の魅力を自ら発信する「TikTok部」が存在する。広報活動の一環として始動したこの部では、企画立案、撮影から編集に至るまでを生徒が主体的に担っている。
学校生活の一コマや行事の裏側、制服の紹介など、発信内容は多岐にわたる。投稿は生徒目線で親しみやすく、ナワガクの空気感をそのまま届けている。フォロワーの増加や再生回数の伸びはもちろん、オープンスクールへの参加者増加にも貢献しており、まさに“生徒による学校広報”として機能している。
またオープンスクールでもその空気は伝わってくる。学校紹介のプレゼンを担うのは生徒自身。言葉に迷いがなく、笑顔と熱意にあふれている。中学生や保護者がその姿を見て「この学校に入りたい」と思わせるエネルギーがある。リアルな表現力と、企画を実行するスキルは、まさにナワガクの探究学習の延長線上にある。



一方で「“他人からどう思われるか”が気になって動けない生徒もまだ多い。だからこそ、まずは“やってみよう”と声をかけることが大切なんです。挑戦が当たり前になったら、人は変わります」
小山先生の言葉には、一貫して「動きながら考えること」への信念が通っている。行動し、仮説を検証し、また新たな問いと向き合う。そのプロセスを何度もくり返すことが、自分らしを手に入れて生きる力になると。
「最終的に育てたいのは、“人生を面白がれる力”」だと小山先生は言う。社会に出れば、正解のない問いの連続が待っている。だからこそ「正しい答えを探す」力よりも「問いをつくり、自ら動く」力を身につける。小山先生を筆頭に、ナワガク自体が新しいスタイルをどんどん更新している。
<取材を終えて>
学園高校の教育は、単なる“自由”ではない。行動すること、問い続けること、その過程で生まれる“自分だけの軸”を育てる環境=“仕組み”であることを感じた。小山先生が語る「青春ってなに?」という問いかけは、探究の入り口であると同時に、その後の人生の道しるべを探すこととも聞こえる。
実際に、在学中の経験を糧に、自らの道を切り拓いている卒業生もいる。たとえば、在学中にゲーム『Minecraft』に熱中し、大阪駅を精巧に再現していた鉄道好きの生徒は、卒業後、関西の私鉄に内定を決めた。また、ディズニーが大好きで「将来は経営者になりたい」と語っていた生徒は、大手旅行会社と連携し、「女子高生がすすめるディズニーの見どころ」を紹介する特設サイトを企画・制作。ナワガクで培った「人生をおもしろがる力」が、社会の中でしっかりと花開いている好例である。
一人ひとりの「やってみたい」が尊重され、それがクラスや部活、仲良しの友達の間で共鳴し、学校全体が“挑戦があたりまえ”の空気に包まれている。もちろん、すべてが計画通りに進むわけではない。だが、うまくいかなくてもやり直せばいい、そんな柔らかさと包容力がある。「まず動く」ことが未来につながると信じる大人がいて、生徒と対話を重ね、変化と成長を楽しむ。不確かな時代を生きるために必要な学びがある。